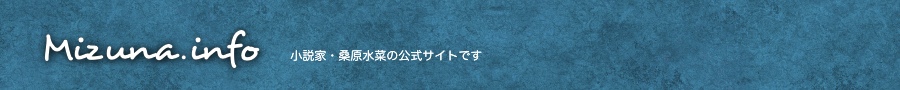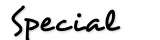舞台『炎の蜃気楼 昭和編 散華行ブルース』を振り返って
早いもので千秋楽から五ヶ月が過ぎました。
Blu-ray&DVDも発売されました。これが舞台シリーズにとっての本当の締めくくりとなりますね。
舞台裏については、同時発売されるミラステ・フォトブックのインタビューや座談会でたくさん語られているので、そちらを読んでもらうのが一番です。(これからご購入の方は、トライフルさんの通販をご利用ください。→ https://shop-ep.net/trifle_stage/ )
舞台の区切りということで、ここからはあくまで私個人の振り返りとして、雑感などを書かせてもらいますね。(ネタバレじゃんじゃんします)
*******
この「散華行ブルース」で舞台「炎の蜃気楼 昭和編」シリーズは幕を下ろし、28年間続いた小説「炎の蜃気楼」シリーズは大フィナーレを迎えました。
公演期間中は大きなアクシデントもなく、無事に全公演を上演しきることができて本当にほっとしましたし、とても濃密で熱い日々を過ごせたこと、心から感謝しております。
一昨年末、原作が環結し、肩の荷はだいぶおりましたが、心の中ではずっと、舞台が無事上演しおえるまでは終わりではない、という気持ちがありましたので、緊張感は続いていました。
最後の舞台は「涅槃月ブルース」と「散華行ブルース」の二冊をまとめた内容で、昭和編のクライマックス。本編で何度となく語られた内容であり、本編一巻へと直接繋がる物語です。これをちゃんとやり遂げることが、ミラージュの本当の環結になるのだと思っていましたから。
全幅の信頼をおくスタッフ&キャストに作品を預け、私はいつも通りご意見番として関わりました。
メディアミックスの難しいところのひとつが、原作者の距離感で、一度預けたら、一切関わらないという方もいます。監修の度合いも様々です。舞台ミラージュに関しても、完全に「観るだけ」になるという選択もありました。でも、原作が好きで観に来る方は、本編完結後も長年にわたって追いかけてくれる、いわば精鋭の読者です。容易に納得させられるものではない。
私は舞台演劇が好きです。だから舞台になったミラージュも、読者の皆さんに喜んでほしいと思いました。
ですから、脚本にも細かく手を入れて台詞の隅々まで「ミラージュ」であることを守りながら「演劇として」違和感のない形にするお手伝いをしました。短い時間の中でそれは想像以上にエネルギーの要る作業でしたが、原作者が納得しないものは読者も納得しないだろうという思いがありました。
ぎりぎりまで続いたブラッシュアップの作業は全員が大変な思いをしたけれど、おかげでより純度高く研ぎあげられた「強いドラマ」になったのではないか、と思います。
また今回のクライマックスである「景虎が美奈子へ換生」という大事件を、演劇的にどう見せるか、という大きな課題があって、稽古前から「どうなるんだろう」と紛糾必至でしたが(みんながみんな、意見がちがうという)全員が納得するまで意見を交わし合い、そう表現することの意味について突き詰めることで、あの形になりました。
ああ、それとラストシーンも。(そのへんはフォトブックの座談会で辻さんたちが語っているので割愛しますね)
今回は初めから最後まで見せ場の連続だったので、大変じゃなかったシーンなど、ひとつもなかったはず。
私は日々の稽古を逐一見ていたわけではないので想像するしかないのですが、あれを作り上げた稽古場は、「赤の神紋」風にいえば「実験場」であり「熱い子宮」というものに等しかったのではないでしょうか。
そうそう。私が舞台版ミラージュにこんなに思い入れをするのは「赤の神紋」という作品を書いたことと無縁ではないのだと思います。あの頃、没頭し、没入して書いてきた物事が目の前で(しかも自分の作品の舞台化という形で!)起きている衝撃ときたら!
いまだったら神紋も、もっとリアルに(特に制作現場を)書ける自信があるのですが、様々なディテールにちょいちょい「これちがった〜」と気づかされつつも、根っこの部分では……核心のところは、そう遠く外れてはいなかったとわかりました。
演劇人と小説家。表現方法がちがっても、根っこの部分というのは突き詰めればやはり、表現者の魂、なのだなあと。
演劇に携わる人たちは、熱い。本当に熱い。
神紋の中で連城にも言わせましたけど、私のように人との関わりが苦手で小説の世界に閉じこもってきたような人間からすれば、演劇人たちは「ありえない」方々で。
大勢の人間が力を合わせてひとつの作品を「創作」するなんて。
人間関係という最も煩わしいもののど真ん中で「創作」をするなんて。
どんだけ強靱な連中なのか、と奥田をみる連城みたいな気持ちで、それまでも演劇畑にいる友人たちを眺めていたんですが、ミラステを通じて気がつけば、自分も連城みたいにカンパニーの一員に迎え入れられていたことになによりも驚いたし、嬉しかった。
ずっとひとりで創作をしていた身ですが、心のどこかでそういう場所に飛び込んでみたかったのかもしれません。
そういう意味でも、神紋の世界を現実の自分が生きてるようで……連城を追体験しているかのようで、とても不思議な気持ちでいた四年間でした。
稽古後、皆で飲み食いしながら今創っている芝居について熱く語り合う時間は、最高だった。
小説家にはない時間だった。
時に愚痴を交えつつも、表現について思いをぶつけあう仲間……むろん皆、プロだから、仲良しこよしのお友達というのとはちがって、ある種の緊張感も勿論あるのだけど(ないと困るのだけど)皆が同じ方向を向いてぶれなかったミラステカンパニーのみんなには、やはり「戦友」という言葉が一番ふさわしい。
私にとって今回の「散華行ブルース」は、特別な意味をもっていました。
今までの四作は、まだ昭和編を執筆している最中だったので、観劇していても、どうしても「(次の巻を書くために)登場人物の感情に見落としがないだろうか」「ストーリーの見落としはないだろうか」と物凄くチェックモードでした。観劇で気づいたことは原作にも反映していたし、そのために集中していました。
しかし今回は、原作は環結した後。
ようやく戦いから解放されて「炎の蜃気楼」という自分が完成させた世界を心から愉しもうと思っていました。
それは同時に「炎の蜃気楼」との訣別の時間でもありました。
自分の半生をかけて書いた「炎の蜃気楼」としっかりとお別れをするために全部を観ようと決めていました。
ずっと連れ添ってきた作品です。キャラクターは皆、自分の一部です。実際、当時は千秋楽から先の自分というのが全く想像つかなかった。千秋楽の座席で逝けたら最高に幸せだろうな、などと愚にも付かないことを夢想することもありました。
千秋楽が終わって、まだ自分は「生きてる」と思えたなら、その先のことを考えよう。ミラージュが終わった先も作家として生きる自分を考えよう。生まれ変わる気持ちで新たな物語を綴っていこう、と。
千秋楽は命日だと思ってた、とどこかに書いたのは、そういう意味です。
景虎や直江がそうだったように、私も一度死ぬ。千秋楽で死ぬ。そしてまた甦る。
舞台が仰木高耶と橘義明まで繋げてくれてよかった。思えば、彼らを生んだのは、景虎自身の「希望」だった。
昭和編のラストシーンがそうだったように、舞台上でも、富田さんが高耶を、平牧さんが橘を演じてくれたのですが、時間にしてほんのわずか、一、二分だったので、今でも幻を見たのかな? と思える時があります。実際、写真も残ってないようなので。
最初の夜啼鳥ブルースの冒頭で、邂逅編を演じた時から「彼らは魂を演じる」という約束ができた。そのおかげで高耶と橘にまでつながった。高耶たちまでもがあの舞台にあがったことで、私の中の舞台「炎の蜃気楼」は完成し、完結(あえてこちらの文字で)したように思えました。
観たかったものは、全部観た。
そういえる今がとても幸せです。
ミラージュという世界に、様々な表現のプロたちが集まって、その力を余すところなく注ぎ込み、出し尽くし、創造性豊かなものに高めて完成してくださったことを、私は「炎の蜃気楼」という「我が子」にかわって御礼を言いたい。
素晴らしい舞台でした。
素晴らしい四年間を、ありがとうございました。
(2へつづく)
- 2019.2.4 更新