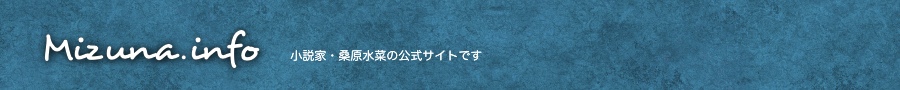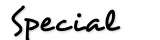カフェへようこそ
公式サイト五周年記念プチノベル
「カフェへようこそ」
作・桑原水菜
校舎に至る銀杏並木が、黄金色のマントへと衣替えをする季節となった。
士官候補生たちの肩に、長袖の冬服がすっかり馴染んできた頃、そのイベントは行われる。
「カフェだって? 本気でやるつもりなのか?」
教室の真ん中で、フォン・フォーティンブラスは思わず大きな声をあげてしまった。
前の席の椅子にまたがって答えたのは、計画書を書くクルダップ・フェフォーだ。
「ああ。おまえが教官のとこに行ってる間に決まったよ。うちのクラスの出し物、カフェ」
「カフェってことは、俺たちが給仕をするのか」
もちろん、とクルダップは胸を張った。
接客業などしたことのないフォンは、当惑顔だ。
「ぐ、軍人が給仕なんて……」
「まあ、いいんじゃないか? 一年に一度の祭りだし」
と横から割り込んだのは、ポテトチップスをつまむジェイクィズ・バーンだ。
「何のための開放日かっていうと、要するに一般市民と交流して、軍の印象を少しでもよくしましょうってことだろ? だったらカフェでもやって、一般市民のおもてなしをするのが一番だ。違うか」
フォンは渋い顔だ。言うことはモットモ、なのだが。
それは、イルゲネス国立軍学校で、一年に一度行われる一日限りの大イベントだ。
軍の施設を一般公開して、市民を温かく迎え入れる「開放日」という名のフェスティバル。一般市民に軍の活動への理解を深めてもらうのが、その目的だ。艦船などの見学会あり航空ショーあり模擬演習あり、さらに模擬店や舞台イベントまで、それはそれは賑やかに開催される。
軍学校もその一環で一般開放されるのだが、候補生たちは必ず、一クラスごとに歓迎の出し物をするしきたりだ。内容は各クラスの裁量に委ねられるので、軍規に触れぬ限り、基本的に自由なのだが、……さて今年のエルフェンバイン一年生。フォンたちのクラスでも、何をやるかで、話は持ちきりだった。クラスによっては芝居をやったり、ホラーハウスなどと凝るところもある。模擬店は割とポピュラーな出し物だが……。
「ただのカフェじゃつまんねーよなー。せっかくだし、なんか変わったコンセプトで行きたいんだけど」
とプロデューサー気分でクルダップが頭を捻る。横からジェイクが、
「仮装カフェとか?」
すかさずフォンが、
「軍人が仮装するのか。いくらなんでも、おふざけが過ぎるんじゃないのか」
「体育祭の時の鎧があるぞ」
「鎧でカフェはないでしょ」
「じゃあ、女装?」
「誰がやるんだ」
クラスメイトの視線が一斉にフォンに集まった。フォンは憤慨し、
「冗談じゃない!」
あーでもないこーでもない、と言い合っていると、そこにニコラスが通りかかった。
「おーい、知恵袋。なんかネタねーか? カフェのネター」
「カフェ? だったら普通に正装してやればいいじゃないか」
クルダップたちはきょとんとした。
「それじゃ意味ねーから言ってるんじゃ……」
「軍学校での訓練の成果を参観してもらうと思えば、制服でいつもどおりにやるのがいい。大体そこまで市民に媚びうる必要があるか。軍人が仮装なんかして、ちゃらちゃらやってたら、かえって国民の信用を落とすだけだ」
「強面でいけ、と」
「当然だ」
まあ、実際そのほうが予算は安く浮くし、貧乏組のエルフェンバインとしては、ありがたいのではあるが。
「ま、この制服も民間人から見れば仮装みたいなもんだし」
やってみるか、ということになった。
*
さて当日。
イルゲネスの軍施設は、どこも朝から花火があがったりして大賑わいだ。パレードの鼓笛隊の演奏も青空に響いている。いよいよ本番だ。軍学校でも二週間前から着々とこの日に向けて準備が進んでいた。エルフェンバイン一年生のカフェも、夜を徹しての飾り付けが完成し、なかなかの出来映えだ。
「おー、盛況盛況」
プロデューサー・クルダップはほくほくだった。なんと開門と同時に、カフェにはどっと人が押し寄せた。しかも、そのほとんどは若い女性たちなのである。すでに長い行列ができていて、普段、女っけのない軍学校とは思えない華やかさだ。
「しかし、三流軍学校の開放日にこんなに人が集まるなんてなあ。みんな暇なのかな」
「いま女の子たちの間で、ちょっと評判なんですよ」
と声をかけてきたのは、愛らしいレースワンピに身を包んだ女学生と見受けられる金髪の少女だ。おっとクルダップは頬を染めた。
「評判て俺たちが?」
「今年の軍学校はレベルが高いって、女の子たちの間ではけっこう話題になってます」
「そうなん? マジそれ」
「中でも凄い注目の御方が、今年の開放日にカフェやるって噂が流れて、もータイヘン」
「あー……なんとなく予想がついてきたけど。君もそのひとり?」
「よう、セレナ! きたか」
振り返ると、調理場にいるはずのジェイクがいる。金髪少女は満面笑顔になって、
「ああああん、きたよおおお、にいさーん!」
「に、兄さん……ってことは、君、もしかしてジェイクの」
「妹のセレナでーす」
途端にクルダップがジェイクの胸ぐらを掴みあげた。
「ジェイクてめえ。こんな可愛い妹がいたなんて、ひとっことも聞いてねーぞ」
「いや別に言うまでも」
「兄さん、なにその格好。ウェイターやるんじゃないの?」
ジェイクは白衣を身に纏い、さながらコックさんそのものだ。
「俺以外に厨房に立てるヤツがいないからさ。俺は裏方」
「がーん。なんだぁ、がっかりぃ……」
「表の様子を見に来たんだ。おー盛況だなー」
カフェは満席。その中で軍服姿に白手袋の、慣れない給仕役たちが右往左往している。その中にはフォンの姿もある。一応、ウェイター経験のあるニコラスから猛特訓を受けて完璧にマスターしたはずなのだけれど、大勢の女子が目をキラキラさせている華やかなムードに圧倒されてか、皿を差し出す手もぎこちない。
「駄目だなあ。あーゆーのは堂々とやればいいのに。ちょっと指導してやろう」
と言い、ジェイクは店に入っていって、フォンを無理矢理、外に連れ出してきた。フォンはほとんど涙目で、すでに弱音を吐いている。
「無理だ、ジェイク。こういうのはどうしていいのか、分からない」
「だから自分がウェイターで相手が客だと思うから調子が狂うんだ。俺たちはあくまで軍人。士官候補生。相手は上官だと思えばいい」
「皿を差し出したら手を握ってくる上官なんているもんか!」
こりゃすでに相当セクハラされてんな、とジェイクはクルダップと顔を見合わせた。
「いいか。手を握られそうになったら、振り払って敬礼しろ。自分の身は自分で守れ」
「何か渡された時は、どうすればいい」
「いいから黙ってもらっとけ。いいか、給仕の所作は全部、儀礼だ。集中しろ。『捧げ筒』な気分でやれ。おまえは軍人だ。いいな」
ジェイクに喝を入れられて、フォンはまた戦場へと送り込まれていってしまった。
「大丈夫かな。フォンのヤツ」
「ま、あれで呑み込みは早いから、なんとかなるだろ」
フォンが戻ると、女子たちの視線が一斉にフォンに集まる。物凄い迫力なので、フォンが引け腰になるのもちょっと分かる。人と関わることにはやっぱりまだ不器用なフォンだが、それでも、こんなふうに少しずつ、距離を縮めていくフォンが、ジェイクには見ていて楽しいし、嬉しい。
いつもなら誰より凛々しい敬礼を見せるフォンだが、今日は少し、よろめき気味だ。
そこへ、
「おい、ジェイク! なにさぼってるんだ。早く厨房に戻れ!」
かみなりが落ちた。ニコラスだ。フライパン返しを手にぶーぶー怒っている。
「さーて、俺も勤労に戻るか。後は頼むぞ、フロア・マネージャー」
「おう! まかせとき!」
一時間もすれば、サマになってくるだろう。
長蛇の列をなすお嬢さんたちを横目に見ながら、厨房に戻る。窓から覗く澄んだ秋の空が、心地いい。
どこからかパレードの陽気な演奏が聞こえてくる。
Fin.
- 2009.9.23 WEB書き下ろし