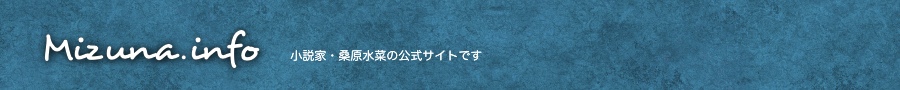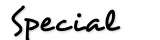不思議の国のカナデ
不思議の国のカナデ
作・桑原水菜
電車がついたのは、見たこともない駅だった。
ここはいったいなんなのだろう。
「だから〝不思議の国〟です」
と言ったのは、電車の車掌さんだった。車掌さんはなぜかケヴァンなのだ。車掌さんの恰好をしたケヴァンが、最後尾の車掌室から半分身を乗り出して、うっとうしそうに答えた。
「ちょっと待ってよ。そんな駅名聞いたことないよ。これ、青梅線じゃないの?」
「乗る前に気がつかなかったんですか」
「だって五番線から出てたじゃん」
「これは〝不思議の国〟行きです」
とりつく島もない。確かに変だとは思ったんだ。電車に駆け込んでから、気がついた。車両はやけにガランとしててオレの他には誰も乗っていない。しかも全然駅に止まらないから回送電車にでも乗り込んだのかと思って慌てた。
そしたら、見たこともない駅についてしまった。ホームはわざとらしいほど可愛らしい。童話に出てくる遊園地みたい。三角屋根の駅舎は、全体に丸みを帯びた淡い色彩。見れば先頭は小さな赤い機関車なんだ。子供電車?
「ねえ、引き返したいんだけど、この電車、戻る?」
「この電車はここ止まりです。帰りの電車はありません」
「困るよ! うちに帰りたいんだ! どうしたら帰れる?」
なら、とケヴァンは電車から降りてきて神妙に言った。
「不思議鉄道の管理局に行って、局長に掛け合うしかありません」
「局長ってどこにいるの」
あそこです。
と遠くを指差した。丘の上に、すごい立派なお城がある。
「でも局長は気難しいから、かえって怒らせてしまわないよう。くれぐれも丁重に」
不思議鉄道の管理局に向かうため、オレは駅に降り立った。見れば見るほど、おかしな街だ。ぶかぶかした地面はパステルピンクで、建物はみんな赤い三角屋根。風船みたいな雲が浮かんで、色とりどりの小鳥が屋根に並んで歌ってる。ここはいったいなんなんだ。
歩いてるうちにすっかり迷ってしまった。
「あの、すみません。不思議鉄道の管理局って、この道を行けばいいんですか」
声をかけた女の子たちはウサギの着ぐるみを来ていた。
「はい、なんですか。あたしたち忙しいんですけど」
「すいません。不思議鉄道の管理局に行きたいんですけど」
「管理局? ダメダメ。あんなとこ行ったら食べられちゃうよ」
黒ウサギの恰好をした女の子は「風音」と名乗った。
「食べられちゃう? 局長って怪獣なんですか」
「悪い魔物なの。しかも鉄道は、局長の気まぐれでしか走らないの。貢ぎ物はある?」
白ウサギの恰好をした女の子は「葛葉」と名乗った。
「貢ぎ物? 困ったなあ。買ってきたばかりのモカちゃんフィギュアならあるけど、局長ってフィギュアとか、好き?」
「局長の好物はひとつしかないよ。それ以外のものは受け取らないよ」
「局長の好物なら、あそこの角の交番で聞くといいよ」
親切なウサギさんたちに頭をさげて、オレは交番に向かった。交番に立っていたのは若い警官だ。警官の名前はケイさんと言った。
「局長の好物? 君なんでそんなの知りたがるの? 命が惜しくないの?」
「帰りの電車を出して欲しいんです。局長ってそんなに怖い人なんですか」
「怖いったら、ありゃしないよ。あの人はこの国を牛耳る魔王なんだ。例の電車でやってきた人はたくさんいるけど、ひとりとして帰れやしない。かくいうオレもそのひとり」
「ケイさんも?」
「うん。下北沢から電車に乗って、気がついたらここに。もう二年も経つよ」
うそでしょ。ってことは、オレも帰れないってこと?
「無理矢理帰ろうして電車を乗っ取ったりしたけど、全部局長に潰されてしまった。一緒にここに来た大事な人は、消息も分からない」
「そんなに怖いの、局長って」
「うん。どうしても帰りたいなら、覚悟がいるよ」
勿論! だって明日から学校があるんだ。帰らないとまた留年しちゃうよ!
「じゃあ、一緒に『局長の好物』を探してあげる。ついておいで」
ケイさんと一緒に向かった先は、電車の整備工場だった。たくさんの人が働いている。整備主任の人と会うことができた。油で汚れた作業着をまとう、金髪の若いおじさん…もといお兄さんだ。その人はジェイクさんという。
「局長の好物を、なぜ俺が知ってると?」
「いえ、ジェイクさんは局長と親友だったと聞いてるもので」
がっこんがっこん、と歯車が回る奇妙な工場の騒音の中で、ケイさんが声を張り上げた。すると屋根でパンタグラフをいじっていたジェイクさんは、ようやく下に下りてきた。
「……カナデと言ったか。君はこの町の独裁者が怖くないのか。まさかあいつの命を奪おうとしてる刺客なんじゃないだろうな」
「刺客? めっそうもない。オレはうちに帰りたいだけです」
本当に? と訝しそうにオレをみてる。じろじろと頭のてっぺんからつまさきまで見て、確かにテロリストにしてはひ弱すぎる、と肩を竦めた。なんか心外だ。
「教えてやってもいいが、表では簡単には手に入らないものだよ」
三丁目のジュンの店に行け、とジェイクさんは言った。「三丁目のジュン」と聞いて、震え上がったのはケイさんだった。
「そんな危ないところには行かせられない! あそこはこの町で一番ヤバイとこなんだ」
「でも行かないと、好物が手に入らないんだよ?」
ケイさんは溜息をついて「なら応援が必要だ」と答えた。どっかに電話をかけてる。警官のケイさんひとりじゃ手に負えないような大変な場所なんだろうか。
確かに大変な場所だった。薄暗い路地には見るからに物騒な人がたくさんたむろっている。おとぎの国みたいな表側が嘘みたいだ。ネオンがびかびか、いかがわしいお店がいっぱい。目のやり場に困るお姉さん方の客引きをすり抜けて、オレたちは歩き続けた。
「こ、こわいよ。ケイさん」
「う、うん。ちゃんとつかまってるんだよ」
私服警官になったケイさんの腕にすがりつきながら、ある路地裏の小さな店に入った。「いらっしゃい」と低い声がカウンターの向こうから聞こえた。暗い店内の壁にはびっしり棚が作りつけられて、そこには大量のフィギュアが並んでるじゃないか。
「ジェイクさんから聞いたよ。局長の好物を探してるってのはあんたらかい?」
え! え! え! 内海じゃないか! カウンターの奥に立つ同い年くらいの少年マスターは、どこからどうみても内海だったのだ。
「なんで内海がここにいんの? 内海も不思議鉄道に乗っちゃったの?」
「は? おまえ誰」
「オレだよ、嘉手納奏! まさか記憶まで失っちゃったんじゃ……!」
「俺の名前はジュンヤ。この世界じゃちょっとは名の知れた違法フィギュアの密売人」
自分から密売人を名乗るなんてそうとうだ。しかも違法ってなんだろう。と目を転ずると、棚の美少女フィギュアが動いてる。ここここここのフィギュア、みんな生きてる!
「おまえが三丁目のジュンか。バイオフィギュアの密売人」
「そこの兄さん、警官? どっかで見た覚えあるけど」
「オレは役者。その気になれば何にでもなれる。こんなふうにもね」
とケイさんが携帯電話を開いてピポパとやると、格闘ゲームのキャラ・コスみたいになっちゃった。ケイさんは変身ができるんだ。
「ここは不思議の国。なろうと思って念じれば、なんにだってなれるんだよ」
「なんにでも? 超騎士にも?」
「ああ。独裁者にも湖底の女王にも」
こいつが局長の好物だ、と内海がカウンターに重い袋をどんと置いた。
「だが法外な値段だぜ。そんな金おまえ持ってるのか?」
お金なんてない。帰りに月見バーガー食べちゃったから百五十円しかない。「これでなんとかならないかな」とオレはさっき買ったモカちゃんの新作フィギュアをおそるおそるさしだすと、
「こここれは、モカちゃんの激レア・浴衣バージョン!」
あっさり交換が成り立っちゃった。こっちの世界でも内海はやっぱりオタクだった。
紙袋に入った「局長の好物」。ずっしり重い。中身は一体なんだろう。店を出て、中身を覗き込もうとしていると、行く手に不穏な気配を感じた。三人の着物姿の男達が立ちはだかってる。
「てめえか、局長の好物を探してるガキっていうのは」
「しまった! 三羽がらす……!」
とケイさん。カラス? 肩を並べているのは、なんか、いちように雰囲気が似た三人組。ちょっと長髪気味で目つきが悪くて、口も悪そうだが性格もひねくれてそうな、この三人。
「左から、新渡戸新、安田長秀、赤毛のアラン。この界隈で恐れられてる局長の用心棒」
ええーっ。たしかになんか三兄弟っぽい。睨まれたら凄いヤな感じのする不良たちだ。
「局長に近づこうなんざ、三千年はえーんだよ」
わわわ。着流し姿の長秀が、スラリと真剣を抜いたじゃないか。
「〝オーギュスト〟はわたさねえ」
と着流し姿にさらしを巻いた新が言う。オーギュスト? それが局長の好物のこと?
「てめえは三丁目のチリになりな」
アランさんが剣を抜いて斬りかかってくる。ガキイッと受け止めたのはケイさんの鉄の手甲だ。「逃げて! カナデ」とケイさんが叫び、オレは背の高い三人の股ぐらをくぐり抜けて、死にものぐるいで逃げ出した。
なんか変だ。なんか変だ。不思議の国って何なんだ。
なにがなんだかわからないうちに、夜の街を走り抜けたオレは、ついに突き当たりのお堀に行き着いた。どでかい城門が立ちはだかる。ここが管理局の入り口?
「そこの君。ここは管理局の入り口だ。何か用事か」
黒い制服に身を包んだ門番が、オレに声をかけてきた。日本人だけど日本人にしてはやけに胸板のしっかりした、やたら腰の位置が高い男の人だ。胸の名札には「NAOE」とある。
「かくかくしかじかで局長に会いたいんです。だめですか」
「局長の好物をもってきたか?」
「はい。ここに」
NAOEという衛士さんは、袋の中身を確かめると、ついてきなさい、と言って門の横の勝手口からオレを中に入れてくれた。あっさりすぎて拍子抜けだ。言われるままについていったけど、なんか様子が変なんだ。
気がついた時には、オレは地下の牢屋に入れられてしまってた。
「うそつき! 局長なんてどこにもいないじゃないか!」
「局長は君になどお会いしないよ。局長の好物はもらっていく。まあ、悪いところじゃないから、のんびりここで暮らすといい」
といってNAOE衛士は去ってっちゃった……。ああ、どうしよう。
どうしようとあたりを見回して、牢屋の中には他にも人がいることに気がついた。
「あの人の言うとおりだよ。抵抗は無駄だ。君も諦めてここで過ごすんだね」
「あなたは?」
「連城響生。小説家」
机に向かって原稿用紙を積み上げてる男前。この牢屋の主ってところかな。
「君も不思議鉄道に乗ってしまったのか。帰ろうというなら無駄なことだよ。俺も局長に会おうとしてずいぶん無茶をやったものだが、とうとうケイともはぐれたきりだ」
「ケイさん? ケイさんて警官やってたケイさんですか? オレ会ったよ! 一緒にここまで来たんだよ」
「ケイは無事なのか! 局長の魔の手に落ちたとばかり思っていた。生きているのか」
「うん。消息不明の大事な人って、あなたのことだったんだね」
連城さんは不意につらそうな顔になり「局長め……」とうめいた。
「俺はここでずっと局長のために小説を書き続けてる。だけど局長の奴は傲慢で、書いた端から駄目出ししまくるんだ。あの男は俺への駄目出しが楽しいだけなんだ。許せない。こんな屈辱を与えるだけ与えて……俺はあの男を倒したい」
そういうことなら、とオレは連城さんにすがりつき、
「あのね、ケイさんがここでは何でもなれるって。頑張れば、ここの牢屋をぶち破れるかもしれないよ。一緒に外に出ようよ」
「外に……。無理だ。局長は恐ろしい奴だ。ぶち破ってもすぐに戻される」
「そんな弱気でどうするのッ。局長の呪縛から逃れたいんじゃないの? それとも駄目だしされるのが気持ちいいとか言わないよねッ」
「そんなわけあるか」
「わかったら、脱出しようよ。見てて。──カナデ・ドキドキ・アターック!」
不思議の国は、なにもかもが一発だ。
どかん、と壁ごと吹っ飛んだ。
崩れた壁の向こうには、それは立派な玉座がある。玉座の正面に座るのは、黒い衣に身を包んだ男。その両脇に控えている二人の若者を見て、オレは思わずアッと声を出した。
局長の隣にいるのは、ケヴァンとケイさんだったんだ。
「おまえがカナデか。私は不思議鉄道管理局長・榛原憂月だ」
物凄い迫力だ。KKコンビを侍らせたハイバラ局長はゆったり脚を組んで、顎上げ気味に見下ろしながら笑ってる。そうそう、悪の帝王ってこんな感じ。しかもケヴァンもケイさんも黒髪な上に真っ黒な服を着てるから三人揃って「黒髪ーず」みたいな迫力だ。
「おのれ、榛原……! ケイを返せ!」
と連城さんが叫ぶ。でもハイバラは意にも介さない。どころか、ケイさんまで不気味な上目遣いで微笑してる。一方のケヴァンも。ただの車掌さんじゃなかったんだ。車掌さんも警官さんも、悪の帝王のしもべだったんだ。
「いかがしましょう。局長。この者は帰りの列車を運行させて欲しいとのことです」
ふむ、と言って局長は顎を撫でながら「オーギュストはあるのか?」と問いかけてきた。局長の好物のことだ。それはさっきNAOEって衛士にとられちゃったんだよ。
「オーギュストがないなら駄目だ。帰りの列車は出せない」
「そんな、困るよ!」
「なら、私の前で演じてみろ。演技で私を納得させられたら、帰りの列車を出してやる」
えええええ──……ッ。
ムリムリムリ。学芸会で「村人2」役しかやったことないのに、そんなのムリ。
「村人2でもいい。演じて見ろ」
ええと、ええと。オレは虚空を指さして
「〝あ、青鬼があばれてる〟」
「運行票は手に入れたぞ、ハイバラ」
オレの熱演を遮って、反対側の扉が開いた。まぶしい。飛び込んできた人を見て、オレは驚いた。アドルフだったんだ。金髪の一団だ。人質にされているのは来宮ワタルくんなんだ。
「不思議鉄道の株は買い占めた。今日から不思議鉄道の局長はこのアドルフ・フォン・ヴァルトミュラーだ」
「貴様、なんのつもりだ。ワタルを放せ」
「それはこちらの台詞だ。こっちにおいで、ケヴァン。君はその男に惑わされているんだ」
「ならん。排除しろ、アンゲロス」
黒い翼を広げたケヴァンとケイさんが、金髪の一団に襲いかかった。大騒ぎだ。どかんどかん凄い音が響いて、なにがなんだかわからなくなっちゃった。たまらず這って逃れようとしたオレの体を何かが上から鷲掴みにした。ケヴァンだ。背中からオレの体をすくい上げた。どさくさにまぎれて、窓を突き破り、外へと飛び去っていくじゃないか。混乱してる人々を尻目に、脱出しちゃった。ケヴァンの翼はぐいぐい力強く滑空する。
「おまえ局長の手下だったんじゃなかったの?」
「俺たちは破壊の天使。最後の列車が出る。おまえはそれに乗って脱出するんだ」
眼下に広がる街は次々と壊れ始めていた。大変だ不思議の国がなくなってしまう。ぽんぽん菓子が弾けるみたいに、お伽の家が飛び交っている。崩れ去る駅舎から最終列車が出ようとしていた。ケヴァンはオレを電車に押し込んだ。
「これが局長の好物だ。これさえあれば、無事に脱出できる」
袋の中身を覗いたオレは驚いた。中にあったのは、壷に入ったぬか床だったんだ。
「ケヴァン、おまえも!」
つないでた指先が離れていく。
うねうね暴れるレールの上を、最終列車が走り出す。崩れていくホームの先端にケヴァンが立っている。オレを見送っている。
「ケヴァ──ン!」
***
で?
とアイザックさんが聞いてきた。
「夢はそこで終わり?」
うん、とオレは答えた。目の前には朝食のテーブル。焼きたてのトーストを頬張って、オレは今朝見た夢を一生懸命アイザックさんに報告していた。
「けっこードラマティックでしょ。支離滅裂だけど映画みたいで楽しかったよ」
「その夢に僕は出なかったの?」
うーん、とオレは思い返して「でなかった」と答えた。アイザックさんは肩を落とした。
「それより急がないと遅刻しちゃうよ。早くお食べ」
「うん、わかった」
オレはトーストを口の中に押し込んで、学ランを羽織った。
電車に乗るときは、君も気をつけてね。
じゃないと、不思議鉄道がやってきてしまうかもしれないからね。
おしまい
- 2008.9.23 WEB書き下ろし