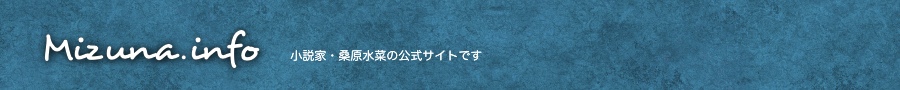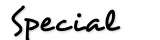嵐の夜
嵐の夜
作・桑原水菜
嵐の夜。
そのとき、響生は窓辺にいた。雷鳴を聞いていた。
巨大なフラッシュを浴びた東京の街が、一瞬、閃光の中に白く浮かび上がる様は、反転したネガフィルムを見るようだ。
雷を怖がった飼い猫のほたるは、響生の膝から離れない。
本物の雷鳴を聞いて偽物の雷鳴を思い出すのは不思議だ。あの日、劇場に轟いたのは熱界雷。人間の手で生み出された凶暴な落雷。その一撃が嵐の海から「生命」を生み出した。
あの日から雷鳴が懐かしい。
榛原憂月の劇場に度々轟く雷鳴は、神の声だと誰かが言った。
地上を揺るがす大音響を体で浴びてみたい衝動に駆られたが、怯えるほたるを置いていくのは可哀想だ。だが響生には今なぜか、あの男もそうしているような気がしたのだ。
ベランダに出て、雷鳴を浴びる。
莫大なエネルギーを全身で浴びる。
今この瞬間、あの男も、きっとこうしている。
*
嵐の夜。
そのとき、フォンは官邸にいた。雷鳴を聞いていた。
デルタ・アゴラの街も激しい雨に煙っている。オレンジ色の街灯で滲む夜空を、稲妻が縦に切り裂き、アインブローデル門の影を鮮明に浮かび上がらせる。
午前四時の元首執務室。窓辺に飾られたイルゲネス国旗を見つめていた。
イルゲネスの雷鳴は、ゲナム山の女神が産み落とした生命たちの産声だ。そう教えてくれたのは養父であるリッテンバー博士だった。
自分は産声をあげたことがあっただろうか。
人間が初めて外の世界で呼吸した時に発するものが産声ならば、自分たちも脱槽した時に発したはずだ。しかし呼吸調整された肺には、その必要すらなかったかもしれない。
何かがこの胸に凝り続けている。
雷鳴を聞いて限りない羨望を覚えるのは、泣き叫ぶことなく生まれ出た命の宿命か。
光学パネルを操作して、モニターに映しだしたのは養父の画像だ。博士、あなたは知っていたのですか。産声をあげずに生まれた人間は、溺れる夢を見ると言うことを。
呼吸がしたい。肺の底から深く深く、息をしてみたい。
呼吸をくれ、ジェイク。
この重い水の底で。
*
嵐の夜。
そのとき、ケヴァンは神社にいた。雷鳴を聞いていた。
冬の終わりに鳴る雷は、春の産声なのだという。この梅香る国で、春は穏やかなるものの象徴だというが、春とは本来激しいものだ。雪解けの川は暴れ、息吹く植物は猛々しい。
石段に腰掛け、ケヴァンは独り、寝静まる街を睨みながら雷鳴を聞いている。
親友も、春の雷鳴を聞くのが好きだった。ヨーロッパの大地で生まれた子供は、春の荒々しさに昂揚感を掻き立てられるのだろう。思い出したのは、親友が好きだった音楽だ。
ストラビンスキーの『春の祭典』。
まだ王座につく前だ。若きアドルフの中に力強いエネルギーの胎動を感じていた。目覚め始めた猛々しい春に、自分は、強く惹かれてしまったのかも知れない。
熟すという未来を持たない自分にとって、荒ぶる春を体現する彼は全てが眩しかった。
春の雷鳴におまえが重なる。アドルフ。
腿の革鞘から『石の刃物』を取りだして、おもむろに立ち上がる。そのとき目線の先で、夜空を真横に駆け抜けた稲妻を、ひと思いに一刀両断した。
何に斬りつけたのか、それはケヴァン自身にもわからない。
古代アステカの石のナイフ。生け贄の心臓を抉りだした、神聖なるナイフ。
この刃がえぐりだすもの、それは……。
*
嵐の夜。
そのとき、景虎は浜にいた。雷鳴を聞いていた。
荒れ狂う波の向こうに小舟が翻弄されていた。木の葉のようだ。どこに流れ着くこともできず転覆するやもしれず、その小舟の運命を浜でじっと見つめていた。
我々、生ける死人は、人の世には関われぬ。
ならば見守るだけなのか。こうしてあの小舟が岩にあたって砕けるまで。あの小舟が波に呑まれて沈むまで。触れることもなく、ただ見守る時間だけはたくさんある。
だが、いずれ嵐は去る。
去ることだけは知っている。ここは越後、冬は厳しく雪は深いが、その冬も必ず去ると知るから耐えられる。耐え抜いた果てには、いつか必ず日が射すだろうと分かるからだ。
この胸の無念も怒りも憎しみも、いつか去る日が来るのだろうか。
横殴りの雨の中、浜の砂を踏む音を聞いた。
いつのまにかその音だけで、背後に近づきつつある者がわかるようになってしまった。笠も蓑も身につけず、このようなところに佇む者は、滅多にあるものではない。
去ることを知らぬ嵐というものは、存外、存在するようだ。
それとも我々もまた、あの小舟に過ぎぬということか。
そうだ。我々は嵐の直中にいる。それが「生きる」ということなのだ。
- 2007.9.23 WEB書き下ろし