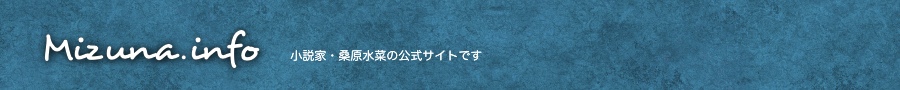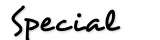夜明けを探しに
夜明けを探しに
作・桑原水菜
ジドラに噛まれて全身にまわった毒は、秘薬アムリタの毒消しで、まもなく解毒することができた。
ケヴァンの首にあった噛み傷も、今はうっすら赤みを残すだけだ。
そしてさっきまで自分が寝ていた座敷には、今度は奏が眠っている。山から戻って疲労困憊の奏は、あれから前後不覚に眠り続け、夜になっても目が覚める気配はない。
ケヴァンはずっとその枕元に座って、奏の寝顔を見つめている。
もう深夜一時。
柱時計の振り子が時を刻む以外は、何も聞こえず、宿坊内は静まり返っている。
奏の寝顔は、お世辞にも「安らかな」とは言えない。苦悶しているのでもないが、目元に残る涙の痕は、消えようとしない。
ああ、そういえば……、
とケヴァンは自分の首筋に残るジドラの噛み痕に指を触れた。
この傷から毒を吸い出したのは、こいつだったな、と。
プロは毒蛇に噛まれた傷を吸い出すことは決してしない。かえって毒を口中に含むことになり、危険だからだ。中途半端な知識でやってのけたんだろうが、あの時は突き放す力もなかった。
ジドラとはギドの左手に寄生する魔物のことだ。御岳の山中で、同じ超騎士であるギドから奏を庇ってジドラの牙をくらったケヴァンは、何者かが名乗らずに置いていった毒消しの秘薬アムリタ(ギドの第三の眼から分泌されるので、要するにギドの涙だ)のおかげでどうにか命拾いした。
でも奏が吸い出して幾らかでも毒が減っていたせいでアムリタも間に合ったのかもしれない。ジドラの毒が奏に効かなかったのは黒い心臓のせいだろうか。
(まさか、な)
吸い出された時のあのくすぐったいような感覚がいつまでも首に残っていて、困った。
髪が泥で汚れている。
守られるだけの子供だと思っていたが、それだけの少年ではないらしい。無茶をしたんだろうな、とぼんやり思った。
内海と美咲に両脇を半ば抱えられるようにして宿坊に戻ってきた奏は、ケヴァンの顔を見ると、悲しそうに少しだけ笑ったものだ。
おまえの言うとおりだったよ、ケヴァン。アイザックさんは、オレを守る騎士なんかじゃなかった。……
それきり倒れ込んだ奏の体を受け止めて、ケヴァンは全てを察した。ゆうべ、奏とアイザックの間に何が起きたのか。
「よく闘ったな。嘉手納……」
深く眠っていて手足は微動もしないが、首から上が心臓の脈動を伝えて、ぴくん、ぴくんとかすかに拍子を打つ。その左胸で動いているアドルフの心臓を想う。
親友だった男の、心臓だ。
やや、ためらいつつも、ケヴァンは眠る奏の左胸に聴診器を置くように、そっと指先をあてた。奏のまだ発達しきれていない胸腔の内側から、拍動する心臓が、とん、とん、とかすかにケヴァンの指先を叩く。その奥で生きている心臓が感じられる。奏の中で動いている親友の心臓。
この手で殺した友の。
(感じる。アドルフ)
そばにいて目を閉じると、アドルフの気配を感じる。いつもそばにあった心臓の語りかける声は変わらない。
責め立てられているようだ。
ケヴァンは沈痛な想いを噛みしめて、立てた片膝を抱えた。
ここにアドルフの心臓がまだ生きているということを、自分はもっと恐れるべきなんだろう。黒い心臓は全てを知っている。止めるために三ヶ月、刺客と成り果てていたこの自分だ。指先に伝わる鼓動に、責めたてられているようで辛い。俺を責めているのは、嘉手納? それとも、アドルフ……? おまえなのか。
(おまえが俺に〝あんなこと〟をしなかったら、きっとこうはなってない)
慰み物にされたとは思いたくないが、ふとそうだったのかもしれないと思える時がある。
親友の心がケヴァンにはわからなくなっていた。彼が変わったことを認めたくなかった。昔のアドルフはもういないのだと、見極めたつもりでも、その奥の闇に迷い込む。実体が捉えられなくなるほど、アドルフの闇は深く大きくなりすぎていた。
奏を殺さなくてよかった。これでよかったんだ、と自分に言い聞かせながら、膝に額をあてた。奏は奏だ。アドルフではない。彼を救ったことは正しかったのだ。だけど不安が募る。
世界中から孤立した気分だ。
(教えてくれ。嘉手納)
アドルフは心臓を抜かれながらもまだアースガルズで生きている。
自分が生きようとするだけで、そのアドルフを殺すことになる奏と、自分は、どこか共犯者めいている。だからなのか?
(俺は共犯者をそばにおいておきたいだけなのか)
そういうことじゃない。とケヴァンはかぶりを振った。なぜなら奏はそう思わない。
なにより、奏はその苦しみを望んでいない。
なにより奏の負った大きな傷の大元に、この自分がいる。
息が苦しい。
ジドラの毒は消せても、心に巣くった毒は消えるどころか広がるばかりだ。時々自分を破壊したい衝動に駆られる。
(これが友を射た報いなのか。アドルフ)
アイザックの憎しみに煮えた眼が、瞼に焼きついて消えない。
──許さない、ケヴァン!
胸に突き刺さる声に、目をつぶって堪えた。
(ザック……)
「嘉手納は目ぇさましたか。神楽崎」
はっとして顔をあげると、開いた襖から内海が顔を覗かせていた。
「あ、そっか。日本語わかんないんだっけ。メンドーだな」
内海はケヴァンの後ろにしゃがみこみ、疎通術が利くよう、彼の肩に手を置きながら、奏を覗き込み、
「嘉手納のやつ、眠りすぎじゃね? 大丈夫かよ」
「血圧も心拍も安定してる。脳が精神的ダメージから回復するために眠りを必要としてるんだ」
内海はケヴァンをじっと見つめている。
ひとり思い詰めていた姿を、内海はずっと隙間から覗いていた。寝返ったというが、そう簡単に信用できず監視しているつもりだった。が、それもだんだん薄れてきた。ケヴァンは膝を抱えるばかりで不穏な兆候もない。何より迷宮事件の時の記憶が内海にはある。
(あの時も、こいつ刺客のくせに、嘉手納のこと守ってた)
「おまえこそ、昨日から、なーんも喰ってねんだろ。ほら」
と差しだした皿の上に、ラップに包まれた不格好な握り飯がある。宿坊の厨房で残りご飯から握ってきたものらしい。
「塩ぬりたくっただけで、なんも入ってねーけど、喰わないよりマシだから喰っとけよ」
ケヴァンは握り飯にかぶりついた。不慣れな内海の握ったおにぎりは、塩が固まりだったり、握る力加減が悪くて、食べるとぼろぼろと崩れたりしてしまって、フィギュアの腕からは程遠い出来だが、ケヴァンは文句も言わずに食べている。
「……回復なんて、すんのかな」
しゃがみこんだまま、内海は同情気味に奏を見下ろしていた。
「嘉手納のヤツ、起きてからがツライんじゃね?」
「かもしれないな」
「胸が潰れるってあーゆーの言うんだな。こいつが号泣するなんて、きっと心臓刺されるより、つらかったんだ」
そんな奏に何もしてやれなかった自分を、内海は悔いている。
「……神楽崎。おまえさ、嘉手納かばったんだってな」
もにょ、と何か言ったが聞き取れず「え」とケヴァンは訊き返した。
「ありがとなっつったんだよ。二度も言わせんなッ」
「別に礼を言われる覚えはない」
「素直に言われとけよっ。こっちだって誰が好きでおまえなんかに」
ケヴァンは驚いて目を丸くした。内海は真剣な眼でケヴァンを見、
「ホントに助けられるんだろうな。こいつのこと」
「わからない」
「なんだとーっ」
「誰も心までは守ってやれない。嘉手納自身が強くならなければ」
奏を見下ろすケヴァンの眼は真摯だった。
「ドナーが生きてると承知で、心臓をその胸に抱えていられるか。試されるのはこれからだ。裏切りの傷を抱えて、本当に乗り越えられるかどうかは」
「嘉手納次第って言いたいのか。俺ら、なんもできねーのかよ。見てるだけかよ」
「下手に手を出すのがためにならないこともある。今は何を言っても慰めにならないだろうから」
敵だったくせに奏のことを自分よりも理解しているようなケヴァンの口振りに、内海はまたモヤモヤしてしまう。
「おまえ、嘉手納のなんなんだよ」
問われて、ケヴァンは少し黙った。奏の補助者、彼を追い詰めた元凶、ドナーの親友だった者……。
「……一口では言えない」
でも、簡単に説明できないからこそ、考え続けるのに違いない。
奏とのことを。
「こいつにあんま深入りすんなよ」
ケヴァンが怪訝な顔をすると、内海はそっぽを向きながら、
「されたくねーんだよ。こいつ支えてやんのは俺の役目なんだから」
「無責任なことは口にするな。おまえにこいつの何が支えられるんだ」
「わかんねーよ。わかんねーけど、おまえにとられたくねーんだよ。俺の役目まで」
ケヴァンは、ぽかん、としてしまった。内海は子供のように、
「嘉手納のトモダチは、この俺なんだぞ」
その一言で、ケヴァンはまた奏の言葉を思い出してしまった。「おまえとトモダチになりたかった」なんて理由でこの自分に命乞いした奏。
なぜ同じことを言うのだろう。
だからなんだというのだ。
友であったがために傷つけられて、友の命を奪った人間に、なぜ執拗に「友になりたい」などと、移植された人間が言ってくるのか。
(──あんな眼をして……)
「………。あいにく俺はトモダチって言葉を信用しない」
「え」
「ずっと見てきたつもりだった。だから誰よりも早く真実に気づいたつもりだった。けど本当はそれよりも……」
ケヴァンが言おうとしていることが、内海にはよくわからない。ケヴァンもちゃんと伝えるつもりはないのか、少し微笑みかけ、
「友なら目が覚める時にそばにいてやれ。それが一番いい」
「おい、どこいくんだよ」
「外の空気を吸ってくる」
というと、座敷を出ていきかけて、あ、と振り返った。
「さっきのが〝おにぎり〟ってやつか?」
「おう。俺サマのお手製だ」
「そうか。甘いのもあるんだな」
えっ! と慌てて内海は皿に残った塩を舐めた。しまった。砂糖だ。
「あいつ、よく喰えたな……」
外は冷え込んでいる。静まり返る山の霊気に身を預けていると、体が清められるような気がする。ふと翼を広げてみたい衝動にかられたが、癒えたての体だ。無駄な消耗はできない。
(償いのつもりじゃない)
ただ死なせたくないと思う。その心臓を持ちながら、トモダチになりたいと言ってきた、ばかのつくようなお人好しを、放っておけない。目の前から失いたくない。
身勝手な理由だ。
わかっているけれど。
(おまえも、本当はそうなんだろう? ザック)
久しぶりに車の音もしない夜だ。眠れる森の梢の上に、星が瞬いている。横たわる黒い巨人のような尾根を見つめ、静寂に身も心も委ねた。
(行こう。嘉手納)
もう当たり前には、夜は明けない。夜の底は深く黎明は遠いけれど、夜明けが見えるところまで必ずおまえをつれていく。
世界の果てまで、夜明けを探しに。
ende
- 2007.6.1 WEB書き下ろし