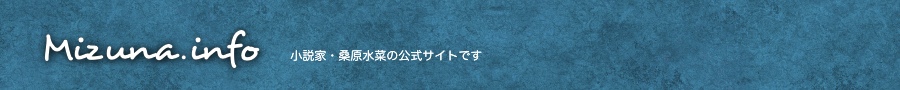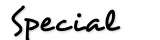CALL ME
CALL ME
作・桑原水菜
「あいすいません。今日はあいにく満席でして!」
軍の給料日であるせいか、今夜の『ホレイシオ』はいつにも増して大盛況だ。酒場の主・ジェイクィズ・バーンは、今しがた店に入ってきた下級士官らしき二人連れに向けて頭を下げた。二人連れはすでにどこかで一杯引っかけてきた後らしく、赤ら顔で酔っぱらい気味に、
「満席ィ? なんで。カウンターの端っこの席あいてんじゃん」
「すんません。あの席はあいにく予約済みで。お一人様なら、なんとかなんスけど」
そんなジェイクのやりとりを見ていたのは店を手伝っていたレイだった。予約? そんなの入ってたっけか。
「しょーがねーなー。また今度来るよ」
「スイマセン。またよろしくおねがいします!」
軍人だの闇市場のバイヤーだの遺伝子工房の職人だので、ジェイクの酒場は今夜も繁盛している。結局店じまいしたのは夜も白々明ける午前五時過ぎだった。後かたづけの洗い物に追われるジェイクに、カウンターの掃除をしていたレイがふと問いかけた。
「この席、予約とか言ってたけど、結局誰も来なかったな」
「ん? ……ああ」
「そういや、この壁際の隅のカウンター席、客が座ったとこ見たことないんだけど」
「そこは万年予約席なんだ」
「万年予約席? 誰の」
ジェイクは小さく笑ったきり、答えない。手はガシャガシャと洗い物に忙しい。
「常連? にしちゃ、一度も」
「常連とは違う。でも、いつも空けてあるんだ。俺が勝手に」
「なんだよ、それ。おまじないか何かか」
「ばーっか。俺がおまじないなんてガラか。その席は座る奴が決まってんだ。この店始めた時から。そいつが、いつでもこの店にやってきて呑めるように」
レイはますます不審そうな顔をしている。
「もしかして、そのひとを待ってるのか」
ジェイクの手がふと止まった。しばし真顔になったが、やがて苦笑いを浮かべた。……レイに言えるわけがない。
「おらおら。お喋りしてねーで、さっさと掃除してゴミ出しだ。そうじゃねーと睡眠時間がどんどん減るぞ」
後かたづけを終えた後の一服は、ジェイクにとって最高のひと時だ。窓のブラインドの隙間から朝日がそろそろと差し込んでくる。賑やかだった夜の余韻に浸りながら、煙草を吹かすひと時の充実感は何ものにも代え難い。
レイは先に屋根裏部屋に戻っていった。今日も一晩ろくにメシも喰わず立ち働いていた。いくら桁外れの身体能力を持つパージ・チルドレンと言えど、人使いの荒いマスターに慣れない仕事で扱き使われてクタクタなのだろう。
ふとカウンターの隅の席を見やった。
今夜も空席のままだった、そのスツール。
(……今日も来なかったな。あいつ)
そう思って苦笑いし、天井をあおいだ。たいがい馬鹿だな、俺も。来るわけがない。相手は曲がりなりにも一国の元首だ。こんな場末の酒場にそうそう顔出せる立場じゃない。
「〝黒の元首〟……か」
口にしてみてもなんだか不思議だ。親友がいまそう呼ばれているのは。
イルゲネスを変えた政変『血の降誕祭』から五年。若き青年将校たちによる首相暗殺事件を皮切りに、瞬く間に軍の実権を掌握し、ついにはこの国の政権を握った男。
現イルゲネス国家元首フォン・フォーティンブラス。
クローン人身売買の温床〝ゲネティック・ソドム〟として悪名高きイルゲネス。ブラックマーケットと癒着して腐敗しきった旧政府を打倒し、イルゲネスの浄化を掲げて、軍主導の新政権を打ち立てた。そのとき、フォンは若干二十五歳。
そして五年後の今──。
彼はイルゲネスの独裁者として、この島に君臨するようになっていた。
「呑みに来いよ。フォン……」
くわえ煙草で椅子に座り、差し込む光の中で舞う埃を眺めながら、ジェイクはひとりごちる。
「その席は、いつでも空けてるんだぜ」
おまえのために。
──そうか……。
俺が軍を離れると告げたとき、おまえの口から漏れたのはその一言だけだった。おまえは止めはしなかった。おまえにはきっと分かっていたんだろう。
あのころ──。一士官候補生というだけで、まだ何の力も持たなかった俺たちは、青い正義感だけで〝革命〟を成し遂げ、新しいイルゲネスへの第一歩を踏みだした。たくさんの血が流れ、たくさんの憎悪を踏み倒しながら、この島を腐敗させる大きな敵を打倒した。その先頭には揺るぎない信念を掲げるリーダー、フォン・フォーティンブラスの姿があった。
命がけの変革だった。
俺たちは戦った。おまえも俺も、イルゲネスのために命をかけて。
そして、おまえの国家元首着任を見届けた時、俺は思ったんだ。
おまえならもう大丈夫だと。
イルゲネスを正しい道に導いて、たしかに、着実に歩いていける。おまえの力は壊すことよりも、新しいものを生み出すためにこそあるはずだ。おまえが、イルゲネスの浄化のために生み出された存在だからというわけじゃない。俺はおまえという「人間」を、見てきたから。
おまえなら大丈夫。イルゲネスを導いていける。
俺の仕事は終わった、と。
そう思ったんだ。フォン。
おまえにも俺の性分は分かっていたんだろう。だからきっと、何も言わなかった。
──俺の夢は店を持つことなんだ。
いつか士官学校の寮で、ジェイクはフォンにそう打ち明けたことがあった。
──店? どんな?
──酒場がいいな。場末の、俺ひとりでも切り盛りできるくらいの、小さい酒場。
──おまえが? だって、ジェイク。おまえ、酒が呑めないじゃないか。
──ああ。人が賑やかに騒いでるのを見るのが好きなんだ。グチでも口喧嘩でもいい。わいわいガヤガヤやってるのが好きなんだ。いつか退役でもしたら、そんな店持つのが、老後の夢さ。
──おまえらしいな。ジェイク。
そういって五歳年下の親友は笑った。その時の話をフォンは覚えていたんだろう。
わかっていたさ、ジェイク。
おまえは、人が憎みあうのを見るのが辛いんだろう? もういいさ、ジェイク。ここからは俺ひとりで歩いていける。
イルゲネスにとって、苦しいのはここからだ。壊すことよりも生み出すことのほうが遙かに困難な道となるだろう。この先どれだけの憎悪と呪いが待ち受けているか分からない。権謀術数、絡み合う思惑、人間はひとつの単純な行為に走る時は強いが、それが成し遂げられて混沌から何かを生まねばならなくなると、途端に自分を見失う生き物だ。そういう中で理想を貫くためには、矛盾と格闘し、軋轢に耐え、争い、時には自ら陰謀に手を染めることもあるだろう。政治とはそういうものだ。
おまえには向いてないよ。ジェイク。
おまえはおまえらしく生きて欲しい。俺は俺の夢を叶える。だから、おまえもおまえの夢に生きろ。
そうしてくれることが、俺の望みだ。
共に血まみれの道を歩きながら、おまえが苦しんでいたことを俺は知っていた。
もう充分だ。ジェイク。
今までありがとう。
大丈夫。俺はひとりで歩いていける。
そう告げて親友は官邸の窓から、ジェイクの姿が見えなくなるまで見送っていた。
あの日から、道は大きく分かれていってしまったけれど……。
(俺が、なんでこの店を開いたか、わかるか。フォン……)
むろん昔からの夢だったって言うのもある。でもそれだけじゃない。
(それだけじゃねーんだよ……、フォン)
きなくさい話は少し前から聞こえていた。
フォンはいつしかイルゲネスの独裁者と呼ばれ、闇市場との癒着が切れるどころか、ますます繋がりを深めている。フォンの軍事政権は、この島のすこぶる高い遺伝子操作技術を利用して、戦争という恐ろしい道を進みつつあるという噂。
何かが違う、とジェイクも思い始めていた。このままでいいのか。イルゲネスが進んでいる道は、本当に正しいのか。
(俺はフォンを信じてる……)
だけど、本当にこのままでいいのか。
そしてジェイクの疑問を具現するように、〝後出者〟は現れた。
フォン、ここはそんなに大きな店ではないけれど、毎晩、客が集まって賑やかになるくらいは繁盛している。
だけど、店を開いた理由はそれだけじゃない。フォン。今も闘い続けているだろうおまえが、一時でも、その心を休める席を、この島のどこかに作っておいてやりたかった。
おまえがここへ来ることはなくても。
ずっと、おまえのことが気になっている。
このままでいいのか。いけないのか。
心が騒ぐ毎日だ。
皆が噂するように、本当におまえは変わってしまったのか。真実が知りたい。
おまえの選んだ道が正しいのか誤りなのか。一年かけて見極めると、俺は言った。
だけど、フォン。そんなことよりも何よりも、おまえのことが気に掛かる。
覚悟はできているんだ。いつだって。
ジェイクは立ち上がると、カウンターの隅の席に歩み寄った。
まだ誰も腰掛けたことのないスツールを撫でて、友のぬくもりを思い浮かべた。
おまえのまわりには、俺なんかより、ずっと優秀で頼りがいのある人間たちがたくさんいることも承知してる。俺なんかにできることは大したことじゃないかもしれない。それでも、おまえさえ願ってくれるなら、こんな俺でもいいなら。
呼んでくれ。一言。
大袈裟なことなどいらない。
俺の携帯通信はおまえのコールのためにいつでも開けてある。
必要としてくれ。いつでも。
おまえのために生きる用意はできている。
酒場の名は『ホレイシオ』。
そう。〈このひどい世界で 苦しい息をつきながら〉戦い続けてきた男の、
親友の名だ。
END
- 2005.11.1 WEB書き下ろし