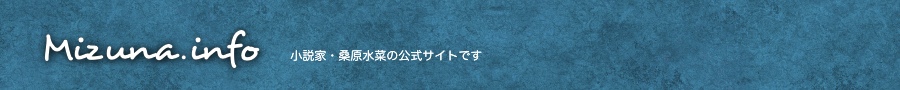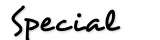お月見をしましょう
サイト開設一周年記念プチノベル
『お月見をしましょう』 作・桑原水菜
響生の仕事が〆切間際になると、黒猫ほたるは大体ほうっておかれる。
世話は一応やってくれるが、エサの時間が午前1時なんてこともある。
シュラバに入ると全然構ってくれないので、せめて寝る時くらいはと、ベッドに入った響生の上に乗ったりして甘えてみる。おかげで響生は、ただでさえうなされ気味なのに、さらにうなされ状態になってしまう。子猫時代ならともかく、最近はずいぶん胴回りが豊かになってきたので、なおさらだ。
飼い主の不規則な生活時間に合わせて育てられた黒猫ほたるは、一年も経つ頃にはすっかり慣れて、マイペースが身についてしまった。
しかし元々、甘えっ子な性分なので、あんまり構ってもらえなくなると、さすがにストレスが溜まり気味になる。
そんなほたるのもとに、格好のストレス解消「天使」がやってきた。
「遊ぼう、ほたる!」
満面笑顔で、ケイは猫じゃらしを手にしていた。
猫じゃらしを見ると、ぴくん、と尻尾を立てて、ほたるのマスカット色の瞳は大きくなる。ケイは稽古場から帰ってくると、進んでほたると戯れる。ほたるにとっては、またとない遊び相手の登場だ。そんなわけで、最近のほたるの運動タイムはもっぱら深夜だ。
「……おまえはなんだか、ほたるのトレーナーだな」
いつの間にか書斎から響生が出てきていた。ケイは、ほたるを抱きかかえて、肉球を押しては爪がニュッと出るのを楽しんでいたところだ。
「おかえり。連城」
「ん? ただいまだろ?」
「仕事場から帰ってきたから『おかえり』。なんか喰う? 昨日のロールケーキの残りがあるけど」
「く……。甘いのはもう。風呂はもう入ったのか」
「帰りがけに銭湯寄ってきた。ほら、広尾商店街の」
「広尾湯か」
「そこそこ。あんたんちの風呂も、うちに比べりゃすげー広いけど、たまに入りたくなんだよなー。こう、浴槽でっかくて洗い場がいくつもあるような。ほらオレ、温泉出身だし」
先日修善寺に里帰りした時に聞いた話だ。温泉旅館の子供と友達になり、毎日こっそり忍び込んではちゃっかり大浴場に入って、風呂代を浮かせていたという。
「夜はひとりだったし。一人で入るのに、風呂に湯張るのもめんどくさくてさ。追い炊きなんてついてなかったし。冬は温泉のほうがあったまるし。母さんの帰りは夜中で、シャワーしか浴びなかったから」
「ケイ」
「はは。ほら、長く連泊する人なんてあんまいないからさ。ちょっと変に思われても、あんまバレないっつーか。あー……」
といっているところにケイの携帯電話が鳴った。ケイが手を伸ばして「もしもし」と出ると、聞こえてきたのは聞き慣れた声だ。
『あー、俺だ俺。奥田だけど、おまえ、明日来んのか?』
「は? なんのことですか」
『あれ? 連城から聞かなかったか? うちの劇団恒例の一泊飲み会。箱根でやんだけど』
「箱根?」
ケイの声に、隣にいた響生があっと気づいて「すまん。忘れてた」と頭を下げた。〆切前のシュラバ中で伝え忘れていたらしいが、なんでも一年に一度、奥田一聖率いる劇団『飛行帝国』では「感謝デイ」と称して温泉旅行に行くのが恒例行事なのだという。劇団員はもちろん、普段、お世話になっている方々も招待されるので、なかなか賑やかなのだが、ついでに、とケイにも声がかかったというわけだ。響生が補足して、
「宴会目的だから、のんびりなんかできないぞ。部屋もほとんど雑魚寝だ。どうする」
「土日は休み。行こうと思えば行けるけど。あんた原稿は?」
「とりあえず差し迫った〆切はない」
ケイは電話に再び向かい「行きます」と即答した。
「い、行くのか!」
「なんで。温泉だろ? ナイスタイミングじゃん。たまにはいいだろ。ぱーっと」
「あのな、『飛行帝国』の宴会は普通じゃないぞ。出入り禁止になった宿が何件あるか!」
「あんた行かないなら、オレ行ってくるけど」
呑み会における役者のノリの凄まじさには、さんざんな目に遭ってきた響生である。なまじ酒に滅法強いので必ず介抱係になってしまう。わかっていても、自分がいないと奥田たちが果てしなく暴走しそうなので、断りきれず参加してしまうのが常だった(←イイ奴だ)。しかしケイも『鳩の翼』で一応は、鍛えてある。基本的につきあいはいいほうなのだ。
「いいじゃん。ホントの温泉入れるんだから。行こうって」
「あー……」
というわけで、響生は不本意ながら「保護者として」ケイに付き添うことになった。
さて翌日。
箱根湯本の某団体向け温泉旅館に『飛行帝国』の面々の姿があった。
「お〜カズ! 来たなぁ! あ、連城さん! 今年は来てくれはったんですね!」
出迎えた『飛行帝国』最年少の瀧沢は、やる気満々モードだ。腕には酒の入った段ボールを抱えている。『飛行帝国』は打ち上げもハンパじゃないが、年に一度の温泉旅行もまたとんでもなく盛り上がるので、お祭りみたいなものだ。
「助かりましたよ、連城さん。去年は俺、ひとりで介抱係だったから」
といったのは今井秀樹である。心なしかげっそりしている。その横から奥田が、
「連城がいてくれりゃ安心して呑めるもんな! ヨシ、今日は呑むぞーっ」
一番元気なのはやはり奥田であるようだ。響生はケイと顔を見合わせた。……なるほどね、という表情だ。
そんなこんなで、とりあえず「ひとッ風呂」浴びた面々は、夕食開始とともに宴会モードに突入した。
「噂には聞いてたけど……」
浴衣姿のケイはボーゼンとしている。
宴会場は大盛り上がりだ。始まった途端にロケットスタートで、三十分も経たないうちにレッドゾーンに突入している。舞台ではカラオケ歌いまくり(←しかも誰も聞いていない)右をみれば怒鳴り合って激論中、左をみれば大泣きして人生相談。正面では瀧沢が踊りまくっている(瀧沢は下戸なので酒は一滴も呑めないはずだが、素で酔っぱらえるようだ)。
「葛川く〜ん」
と女優陣がここぞとばかりに集まってきた。女といえど、そこは『飛行帝国』の役者なので、勢いがちがう。あっと言う間に、ケイは年上女優たちに囲まれた。
「一緒に混浴しませんか!」「なんなら部屋に戻って!」「それより散歩行こうよ。おみやげ屋めぐりとか!」「ゲーセンでもいいよ!」「卓球卓球!」
おい、こら。と奥田が向こう正面から怒鳴りつけた。
「勝手に持ち帰んなよ。そいつは不祥事厳禁中なんだから」
え〜つまんな〜い。と女優陣が声をあげる。そこにすかさず瀧沢が駆けてきて、
「おまえらにカズは独り占めさせへんで!」
とケイの横に座り込んで弾丸のように喋り始める。ふと視線を外すと、響生の周りにも外部スタッフらしき人々が集まってわいわい盛り上がっている。へー、意外に人気あるんだな、とケイは変なところで感心した。そんなこんなで宴は最高潮になり、だんだん座も乱れてきた頃だった。
「ケイ」
あちらで盛り上がっていたはずの響生が、いつの間にか横にやってきている。腕を引っ張られてケイは立ち上がった。
「な、なに」
「そろそろ大騒ぎになるから、巻き込まれないよう、先に外に出ておけ」
つまり沸点まで来たと言うことか。確かに乱れっぷりが尋常でない。瀧沢たちは裸踊りを始め、女優陣なども酔いが回ってあられもない姿になってきているが、皆、おかまいなしだ。
「な、なに。そんなにスゴイの」
「器物損壊はあたりまえ。柱に登る奴とか、池に飛び込む奴とか、わけのわからない芸始める奴とか、目も当てられなくなるから。……あいつらとのつきあい続けたかったら、このへんで」
はあ……、とケイは気圧され気味だ。響生もげんなりしつつ、
「介抱役はそろそろ忙しくなるから、いまのうちに風呂でも入ってのんびりしておこう」
*
この旅館は、大浴場と露天風呂が別々のところにある。露天風呂は別棟にあり、日帰り湯もできるようになっているのだが、様々な種類の風呂があり、まるで健康ランドだ。さっきも入ったのだが、樽風呂だの寝風呂だの滝風呂だの、目移りして、ケイは大はしゃぎしてしまった。檜の枕が気持ちいい寝風呂がお気に入りのケイは、またそこに入ろうと言い出して、結局もう一度、露天風呂に行くことになったのだが……。
風呂までは、結構長い回廊を歩かなければならない。
その途中のことだった。
向こうから歩いてくる浴衣姿の二人組に、ケイと響生は「えっ」と目を剥いてしまった。
「なあ、連城。あれ、誰かに似てないか」
「ああ……。まさかと思うんだが」
「目の錯覚かな」
「いや。他人のそら似でも、あんな二人組、そうそうあるわけがない」
向こうから歩いてきた二人組のうち、華奢で小さいほうが「あれ?」と高い声をあげた。
「葛川くん? そこにいるの、葛川くんじゃないの?」
ケイと響生はあんぐり口を開いてしまった。
目の前にいる浴衣姿の二人組。
「く、来宮くん?」
ケイはア然としてしまう。
「は……榛原憂月」
響生は絶句してしまった。
マイ桶を抱えた浴衣姿の榛原が、ふたりを見て、目を丸くした。
「なんだ。来ていたのか」
*
「なんだ。来てたのか。……って、なんか文脈的に間違えてるよね」
と言ったのは、貸し切り露天風呂の湯船に身を沈めた来宮ワタルだった。
「だって、葛川くん達は偶然たまたま今日初めて来たわけだよね」
「あの人にはなんでもお見通しってことなのかな」
その隣で湯に浸かっているケイが、ぼんやりと庭木を眺めながら言った。
「まさかクレセント・カンパニーまで慰安旅行に来てるとはね……」
旅館で鉢合わせてしまったライバルふたりは、いま、仲良く同じ風呂につかっている。榛原はちょうど貸し切り露天風呂に行こうとしていたところだったらしい。尤も、人と一緒に風呂に入ることはしない榛原なので、ワタルは一般用露天風呂に行くはずだったのだが、榛原はなぜか、ケイとワタルに貸し切りを譲り、響生をつれて、部屋に戻っていってしまった。
そんなわけで、ケイとワタルは、一緒に貸し切り風呂に入っているのである。
「慰安旅行っつーか、宴会かねた合宿? 昼も稽古させられたし」
「あ、そっか。さすがクレセント・カンパニー」
「芦ノ湖で発声練習だよ? カンベンしてほしいよ……」
ワタルは湯船に首までつかって、いまにも沈みそうだ。それにしても、欧米人の血をひくワタルの白い肌は、湯船の中でもまぶしくて、ケイはちょっとドキドキしてしまう。ほんのり染まる頬に、濡れた髪から滴がつたうのも、なんだかそこいらの女性よりも色気がある。
ケイはまた見とれてしまった。
「え? なに?」
「あっ。いや……温泉美人だなー…って思って」
「温泉美人? 俺が?」
ワタルは途端に弾けたように笑い出した。
「かっ葛川くんて時々天然だよね」
「ごめん」
「いいよ。温泉玉子とか言われるよりは、ずっとマシだもんね」
「えっ。だれかに言われたの」
「榛原さんに」
「は」
「こないだの稽古で。『この温泉玉子』って。イミわかんないよね。時々あるんだ。榛原さんの謎の駄目出し。……謎じゃ駄目なんだけど。半熟とか中途半端ってことなのかな」
まあ、言っている本人からすれば突拍子がないわけではないのだろうが、言われたほうはやっぱり首を傾げてしまう。
「白いから余計に玉子かもね。いいな、葛川くんは。肌の色も適度に焼けてて健康的なカンジ」
「よく炎天下のバイトとかやってたからなー…。これでもだいぶ白くなったんだよ」
「俺ももう少し黒くしたいけど、日焼けすると赤くなっちゃうんだ。じーちゃんカナダ人だから。小学四年まであっちにいたし」
「えっ。マジ? だから英語ぺらぺらなんだ」
他愛ない会話をしていると、お互いがライバルであることも忘れてしまう。
ふたりは肩を並べて温泉につかっている。
松の梢の先に、月が見えた。
なんだか風流だ。
「たまにはのんびりするのもいいよね……。葛川くん」
「うん。たまにはこういうのもね」
広い檜の湯船で、のびのびと手足をのばし、ケイとワタルはゆだりきるまで、気持ちのいい湯に浸かっていた。
*
酌をしろ。
と榛原に言われて、部屋まで連れてこられてしまった。
響生は部屋の真ん中で固まってしまっている。
なんでこんなことになってしまったのか。
鉢合わせた、といっても榛原たちの宿泊先は、別館の○○亭なる、眺望もお値段も高めの部屋だったようだ。さすがクレセント・カンパニー、泊まるところも違うな、この野郎。と響生は内心、感心している。しかも榛原の部屋は離れときた。奥田に見せたら、暴れそうだ。
「いい湯加減だったぞ。クラウデス。おまえも入ってきたらどうだ」
結局、榛原は部屋付の風呂に入ると言いだした。
「ここからでも充分、いい眺めが楽しめる。月が美しいぞ」
二間続きの広い部屋だ。床の間には、お月見の季節だからか、ちゃんと月見団子とススキが飾られていて、隣の部屋には、もうしっかりと布団が敷かれてあった。
しかし響生は部屋の真ん中で、戦々恐々、緊張気味に正座している。
「……なんであなたの酌をしなければならないんですか。榛原さん」
「敬語はやめろ。みろ。月が高くなってきた」
というと、榛原は冷酒と杯を載せた盆をとり、縁側のガラス戸を開けて、座り込んだ。いい風が入ってきた。榛原はガラスの盃に冷酒をついだ。
「風にススキが揺れて心地いい。風流を楽しもうと言っているのだ。来い。おまえも呑め」
と振り返って盃を持ち上げる。
響生は、しかしそんなに簡単に警戒を解くわけにはいかないのだ。人のことを酒の肴にでもする気なのだろうか。油断ならない男なのだ。何を言われるか、気が気でない。大体、こんなところを渡辺に見つかったら、何を言われるか分かったものではない。
「渡辺なら、さっき帰った。プロデューサーはおちおち温泉にも浸かっていられないな」
と声をあげて笑う。もうすでにほろ酔い気味らしい。呑むと、意外にも笑い上戸になる榛原は、酔いが回るとえらく饒舌になったりもするのだが、どうやら格好の話し相手を見つけて機嫌がよくなってしまったようである。旨そうに冷酒をクイと傾けた。
「秋だな」
虫の音がにぎやかだ。
「いい月だ。車を出せれば、仙石原のススキ野原で見たいところだが、今夜はここで我慢しておこう」
ほら、と自分が呑んだカラの盃を、響生のほうに押しつける。響生が仕方なく受け取ると、榛原は手ずから冷酒を注いだ。浴衣姿でも榛原は襟をくつろげることはない。正月の和装のようにきっちり着こなして、しかも、なかなかに似合っている。徳利を傾ける姿は男前だ。
「そんなに構えるな。今日は気分がいいんだ。無粋なことはいわん」
確かに今日の榛原は滅法、機嫌がいい。響生は根負けして、盃をあおった。喉ごしのいい吟醸酒だ。さっきまでの宴会で呑んでいた酒とは大違いだ。
「今宵は十六夜だな。月はやはり秋がいい。冬もいいが、遠くて鋭すぎる。三日月ならばいいだろう。春は霞の中にぼんやり滲んでいるのがいい。夏は、夕焼け時だな」
「あなたの名前」
ん? というように、榛原は響生を見た。
「憂月という名前。ペンネームだと聞きました。本名はどこにも明かしてないようですが」
榛原はしばし月を見つめて、微笑した。
「明かす必要もないからな。私は己に名を付けた。その瞬間、私は私を生んだのだ。いまはこの名以外で生きるつもりはない」
親につけられた名前は、勿論、住民票だの契約書だのの公文書には使っているだろうが、それを知っているのは大学時代からつきあいのある渡辺たちくらいだろうか。
「名前の由来は、確かベートーベンだかのソナタからだとか」
「よく知ってるな。どこで調べた」
調べるもなにも。榛原のインタビュー記事は逃さず集めてきた響生である。しかし本人に言うのは憚られるし、ちょっとシャクだ(……今更だが)。
「……思い入れのある曲だ。それが弾きたいばかりに独学でピアノを始めた」
「あのピアノ」
「実際曲名をつけたのは本人ではないらしいが。私はあれに『月光』と名付けた人間を素晴らしいと思う。第一楽章は私の子守歌だった」
というと、榛原はまた一献、冷酒の盃を傾けた。
月明かりにふちどられた横顔に、響生は不覚にも、しばし見とれてしまっていた。
この空気はなんだか不思議だ。
まさに天空に浮かぶ月のような存在だった人間が、目の前にいて、酒を呑んでいる。
月を愛でる、か。
「……愛でるというか……」
「なんだ。ひとりで納得するな。いいから呑め」
結局、酌をするどころか、されている。妙な気分だ。
静かな夜だ。奥田たちのところでは今頃、大荒れになっている頃だろうが、あの台風並の騒ぎを免れることができたのは、或る意味ありがたい。まあ、相手が榛原では皆も文句のつけようがないだろう。すまん、今井。と心の中で拝んでいたら、榛原が横からこう言った。
「今夜は心いくまで呑むつもりだ。潰れたら、後は頼む」
……介抱役には変わりないということらしい。
ちょっと途方に暮れながら、まあいいか。と響生は思った。
こちらが潰れてから戻っても、遅くはないだろう。
それに本音をいえば──。
こんな間近で、時を忘れて、この男の横顔を眺めているのも悪くない。
と思っていたそのときである。
バタバタバタと回廊のほうから誰かが駆けてくる音がした。がらり、とドアが開いて、榛原の部屋に飛び込んできた者がいる。
「たたた大変です、榛原さん! 来宮くんが風呂でのぼせちゃって……!」
ケイだった。
榛原はちょっと目を丸くして、おもむろに立ち上がった。
「世話の焼ける奴だな」
といって羽織に袖を通し、下駄をからんころん鳴らして、部屋から出ていってしまう。
響生はケイと顔を見合わせている。
まあ、たまにはこんな夜もあるということだ。
湯気の向こうには、美しい月がにじんでいる。おわり
- 2005.9.23 WEB書き下ろし