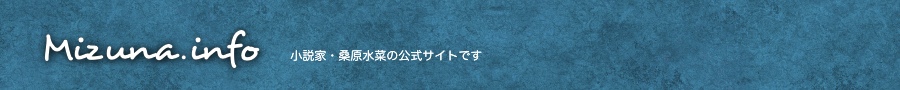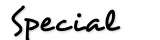20歳の月
「20歳の月」 作・桑原水菜
それは不思議な夜だった。
真冬だというのに風がふわりと暖かく、まるで突然、春がやってきたような夜だった。
四万十川の水面に映る月も、あの冴え冴えとした輪郭はどこへ消えたのか。
不意の暖かさに気でも緩んだように、ぼんやりと滲んでいる。
「これで桜でも咲いていれば完璧なんだけどな」
高耶が言った。テントから離れて、川縁の岩に腰掛けている。
呼び出された直江は、少し当惑しているようだった。
「あの……。緊急の用件とは何でしょう。作戦の変更でも?」
「用件は、こいつだ」
高耶が差し出したのは、日本酒の瓶だ。地元酒蔵の名が入っている吟醸酒。どういうことなのか、と直江は首を傾げている。
「あの……。酒がどうかしましたか」
「どうかじゃねーだろ。酒は呑むものだ」
「なに言ってるんですか。あなた未成……」
と言いかけた口に、高耶が酒瓶を突き付けた。にや、と笑い、
「いつまでガキ扱いしてんだよ。もうとっくに20歳だ」
そうか、と直江も我に返った。二年ほどの空白があったため、忘れがちだが、高耶はとうに成人している。
「おまえには昔、カクテル奢ってもらったことがあったしな。借りを作ったままにしとくのは好きじゃない」
「ああ。松本でのことですか。よく覚えてましたね」
「あの頃のおまえ、大概えらそーだったよな。未成年に酒呑ますなんて通報もんだぞ」
もう時効です、と言って直江も隣に腰掛けた。猪口もないので紙コップだ。いささか情緒にかけるが「アウトドアっぽくていいだろ」と高耶は屈託ない。返杯を受けた直江が、苦笑いして、
「珍しいですね。今夜はいつになく」
「風のせいかな」
昨日まで凍えていた体が、春の陽気で不意に緩んだせいだろう。いつもはぴりぴりしている高耶も、今夜は不思議に和んでいて、川風を心地よさげに受けている。
「……おまえと一度、こんなふうに呑んでみたかった。未成年とか窮屈なこと言わないで、対等に」
「この体に換生する前は、よく呑んでましたけどね」
「ああ。でも今のおまえとオレで、呑みたかった」
月を仰いで、また一献。水のように癖のない、澄んだ酒が喉へと滑り落ちる感触を愉しんでいる。ほろ酔いの瞳に朧月を映しながら。
「上杉の肩書きもない、ただのおまえとオレで、呑みたかったんだ」
「なるほど。これはあらためて固めの杯というわけですか」
「そういうことにしといてもいい」
今更必要もないが、と直江は苦笑いを浮かべた。
「……桜があると、なお、いいですね」
「なんなら咲かせてやろうか」
高耶が悪戯をするような眼になった。「おまえのなかに」
これはいけない、と直江は思った。気を抜くと、呑まれてしまうのはこちらかもしれない。高耶はこれでいて酒に強いのだ。
「安心しろ、直江。潰れたら介抱してやる。もうオトナだからな」
小生意気な口を利く高耶を見て、時が束の間、巻き戻った想いがする。今夜はこのまま憎まれ口を聞いていたい、と直江は思った。
酔って潤んだ瞳に桜吹雪が見えてくる頃には、もう微睡みが訪れていることだろう。
主従で交わす、春の杯──。
朧月に、幻の夜桜。
乱れ咲くも、散らすのも、全ては互いの心次第だ。
- 初出 サイン会用書き下ろし(雑誌『Cobalt』2011年9月号掲載)
- 2011.4.30 WEB再録