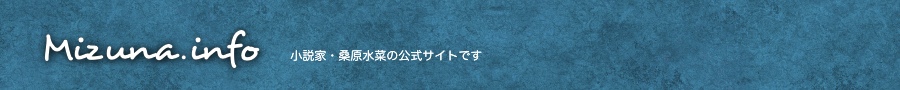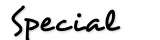おおみそか
おおみそか
桑原水菜
真夜中の闇を伝わって、どこか遠くのほうから聞こえてくる──。
重く夜を揺さぶり、高く乾いた波長と一緒に余韻が静かにやってくる。
鐘の音だ。
と思ったところで目が覚めた。体温で充分温まった布団のぬくもりの中で目が覚めた。
「……起きましたか」
すぐ側から直江が声をかけてきた。ひどく部屋の中が静かだった。外に出している顔だけがひんやりして気持ちいい。直江は隣の布団に座っていた。高耶と同じ浴衣姿で、肩から羽織をかけたまま、テレビもつけずにずっと本を読んでいたらしい。
「いま何時」
「十一時四十分です」
「ああ。あと少しだな」
夕食の熱燗が効いたのか、いつのまにか眠ってしまっていたらしい。温泉に入って温まったらどんどん眠くなってきて、気持ちよくて布団の中に倒れてしまった。確か九時くらいだったから二時間半は眠ってしまった。その間、直江はひとりで本を読んでいたらしい。
「間にあってよかったですね。十二時まであと二十分です」
「あ……紅白」
「え」
「あ、いや、うちの大晦日、毎年無理矢理紅白見させられてたから」
「同じですね。うちも紅白から『ゆく年くる年』の流れを見ないと年が明けた気がしないんです。もうフィナーレだと思いますが……つけますか」
高耶は布団の中でしばし考えた。
「……いい。このままで」
「そうですか」
「なんか……いいよな。こういうのも」
布団から抜け出さないまま高耶は呟いて、まぶたを閉じた。
(静かだなぁ……)
何も考えずにのんびりできるところ──という高耶の希望で直江が選んだのは、古くからの温泉場として知られた中伊豆の小さな町だった。老舗旅館。と最初聞いたときは「格式ばってて肩凝るかな」と心配した高耶だが、意外にもこれがとても居心地いい。何もせずにごろごろしているだけで気持ちが休まる。なんのせいだろうと考えて、やはり建物の醸す空気だと思い当たった。田舎で農家をやっている祖父の家を思い出す板張りの天井、年季の入った柱はいい具合に色が出て落ちつく。古い床の間、古い掛け軸。そして高耶が一番気に入ったのは、ガラス戸だった。木枠にはまった薄いガラス、拳を軽くあてたら氷のようにパンと割れてしまいそうな、少しの風でカタカタ言いそうな、頼りないガラスである。なんていうことはない。ほんの四十年くらい前の家は皆これだった。でもサッシにとって代わられた今となっては、懐かしいと言うほかない。障子には雪見窓がついていて、これもまたいい風情だった。
身の丈にあった、というのか。漆喰の壁も、鴨居や柱も……長い歳月に洗われた岩のような柔らかさがある。心が落ちつく。
そして静かだ。
「除夜の鐘」
「ああ。聞こえますか?」
「耳はいいんだ」
ふたりは黙って、少し夜の静寂の向こうに耳を傾けた。ほんとうにかすかだが、聴こえる。
伊豆の山間の、古い小さな温泉町に響いていく除夜の鐘……。
そう。遠くで聴く、梵鐘の音は不思議だ。
ほんとうに静寂に波が押し寄せてくるようだ。細い細い入り江に吸い込まれていく波のように、胸に吸い込まれていく。
「……修禅寺の鐘ですね」
静まり返った旅館には、他に音はない。車の音も、しない。
高耶は息を吸い込むようにして鐘の音を耳に受けた。直江も耳を澄まして冷たい空気の中に響く鐘の余韻を味わっている。
「いつもは打つほうですから。こんな風に聴くのは久しぶりです」
すると高耶は笑った。小さい声でおかしそうに笑った。
冷え込むなと思って直江が雪見窓を開けに立つと、庭にうっすら雪が舞っている。ナナカマドの枝がかすかに白くなっていた。伊豆は温かいはずなのに、寒波でも来ているのか。小雪の大晦日となった。
また、ひとつ。
除夜の鐘。
「いいよな。こういうの」
布団の中の高耶が、もういちど呟いた。
「こんな年越しも……わるくない」
直江も微笑した。
静かに静かに1998年が終わっていく。
「初詣、行きますか」
「ああ。年が明けたら、すぐ、な」
「零時から修正会を行うそうですよ。甘酒も振る舞うそうです」
「甘酒ッ?」
「あなたの目的はこっちですね」
布団の中から高耶が睨む。そうこうしているうちに、時計の針は午前零時のところで重なった。
ふたりは顔を見合わせた。
「明けましておめでとうございます」
直江が言うと高耶も相変わらず布団の中で「おう」と答えた。
「今年も……よろしくな」
おわり
- 初出 『FAX版上杉藩御用達』1999年1月
- 2005.11.1 WEB再録